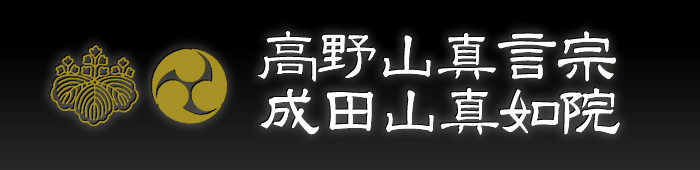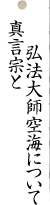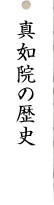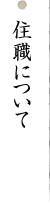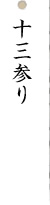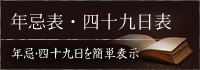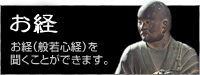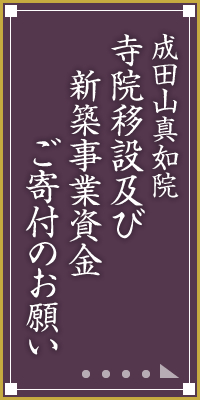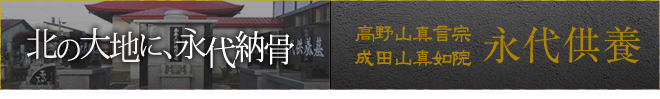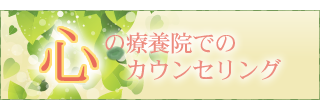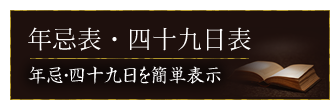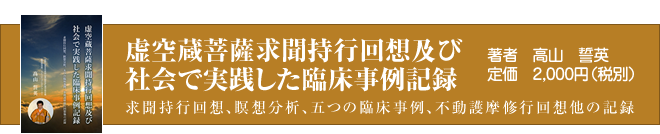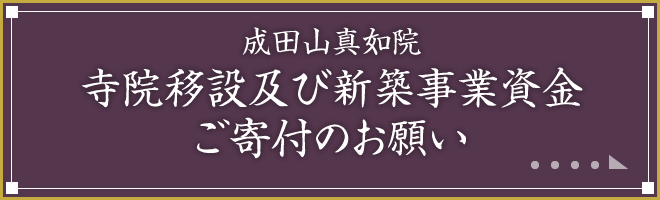「ブータンの葬儀とダルシン」
〈更新日: 2013年6月5日 〉 ※写真が掲載されている場合は、クリックすると拡大表示されます。
~“祈りの国ブータンへの参拝旅行紀行記” 住職 高山 誓英の記録~
ドルジさんにブータンの葬儀について聞いてみた。
このテーマは、私にとって今回の重要なテーマの一つとして位置づけしている関心事項だ。
「葬儀」は、どの人にとっても一生の中での一大行事である。
今日の日本では、宗教、僧侶いらずの商業化した葬式、葬儀社まかせの温かさを感じない人工化した葬式、バカ派手か何もしない簡素化した葬式、儀式なしの直接火葬にするだけの葬式が流行だ。
さらに散骨と称して遺骨を産業廃棄物のごとく、まるでゴミのごとく捨て去ったり、親族と関わりを否定した無縁遺骨、無宗教と称して信仰を排除した埋葬儀式、商業化に乗っかり金銭売買によった事務処理的な遺骨処理等どれをとっても人間の生命の尊厳を否定しているものばかりである。
「葬式、埋葬とは一体何なのか」が問われている現実を見る。
このような心を無くした葬式、埋葬の背景には「人間の尊厳である生命を尊ぶ」という宗教的原点を日本人が見失っているところにある。
宗教を信じるということは、 「自分が信じる心の拠り所を下に、自分の生命の息遣いを感じ、他者の生命の尊厳を尊び、自分と他者との生命とのつながりを感じる」ことを言う。
最近の中国の人達の行動についても同じように感ずるものがある。
それは拝金主義にもとづく心を失った無味乾燥化した社会行動が非常に多く見られることだ。
中国国内のヒソ、水銀等の産廃タレ流し事件、メラミン入り粉ミルク事件、毒入りギョーザ事件など考えられない事件が平然と起きている。
そして尚且つ、同様な事件が今なお頻発して歯止めの利かない状況にあり、中国国内で自国の業者が生産した製品を中国国民自身が全く信用していない情報を知る。
文明国と称する自慢の国々が、こうも人間性を失った非常識な問題が多いのは何故なのか。
この答えを探す為にもブータンで問いかけてみた。
「ブータンでは、殺人事件は、過去にも現在でも一度も起きていない」
「ブータンでは、宗教上から牛も豚も殺さない。だから人殺しなどありえない」
「そして魚つりもしないし、根物の野菜も食べない」
「これは、生命を人為的に絶つことは許されないことを宗教が教えているからだ」と説明があった。
このような密教信仰にもとづいた日常生活の中に生きる葬儀儀礼について尋ねた。
葬儀は、亡くなるとそこの家に数十人の僧侶が出向きお参りをする。
通夜、葬儀と2日かけて約20~30人僧侶が2日間朝から夜まで供養のお参りをする。
葬儀が終わると遺体は、川の側にある火葬場で焼き、遺骨はそのあとすぐに川に流す。
この意味は、自然からいただいた肉体は、また自然の元に帰す意である。
だからブータンにはお墓がない。というより必要がないのである。
しかし、肉体から離れた魂(生命)は、まだこの世(中有)にいて落ち着いた世界にたどり着いていない。
その為、亡くなった日から21日か49日までの毎日、約10数人の僧侶を家に招いて、供養のお参りをして亡くなった人の魂を慰める。
この意味は、亡くなった人の魂を慰め、仏様の世界(自然)で永遠に生きるようにと願って行う供養である。さらに供養のお参りが終わった証として、白い色のダルシン(白い旗)108本を、毎日お参りが終わった直後1本づつ高い山の上に掲げる。
だから3千メートル級の山々にはダルシンがいたる所でなびいている。(ダルは、旗。シンは、風の意味)
僧侶達へのお布施は、葬儀では数百万円近く49日までのお参りにも数百万円近いお金が掛かるそうだ。
だから、一人の葬儀の為に掛かるお金はすごい金額になるといっている。
「何故、そんなにお金を掛けるのだ」とドルジさんに聞いた。
「私達は、仏様から生まれてきました」
「死んだら私達の生命は仏様の世界に帰ります」
「そしてその後は、仏様の世界で永遠に生きて行きます」
「別の言い方をすれば、仏様の世界で永遠に生きて頂く為の生活費を仏様
に預けるのです」とドルジさんは言う。
「ですからお金が掛かります」
「人間には、必ず死を迎える時間が来ます」
「ブータンの人は、自分の一生の間にその為のお金を貯めておきます」と言う答えが帰ってきた。
ブータンの人たちの所得は、日本人の約1/10位と推測する。
それなのに一生で稼ぐ所得のほとんどを葬儀のために使うことになる。
私達日本人にとっては、考えられないことだ。
しかし、そこまでして「生命の尊厳」に対してお金をかけるようとするブータン人の心の有り方、ブータン国民のアイデンティティーに頭が下がる思いがあった。
ちなみに僧侶は、国家公務員であり、僧侶は国から安い給料をいただいている。
そしてあらゆる布施は、集められて全て一度国に入るようだ。
国は、集まった布施を、山の上のお寺や修行僧や多くの僧侶を養っている全国のお寺に配分すると言う。
日本では、お寺は独立採算による法人経営である。
その為、お寺の住職の大部分仕事は、お寺を経営することに大きな比重を占める。
しかしブータンでは、国がお寺や僧侶の面倒を見るので、お寺や僧侶が本来行うべき布教活動や寺院行事を安心して行うことが出来る事に気付かされた。
日本の住職の仕事は、どうしても経営や経済活動が中心にならざるを得ない。
その為「本来行うべき布教活動、僧侶自身の修行、資質を高めること、人々の救済」にまで手が廻わらない現実がある。
実は、この事が日本のお寺や僧侶の問題点であり「僧侶は、金儲けばかり行っていて、布教や人々の救済をしていない」と非難される。
だから「既成仏教は、国民に根ざしていない」と言われるのである。
ブータン人の信仰の篤さ、祈りとともに暮らす生活習慣に溶け込む密教の教え、どれをとっても日本人が見習う必要のある行為と言える。