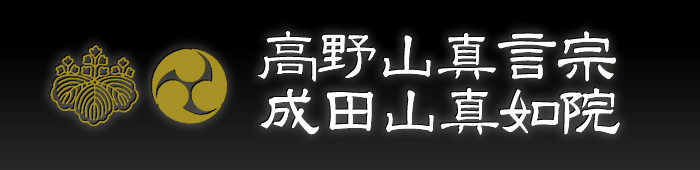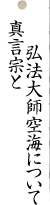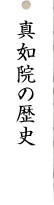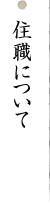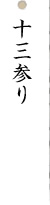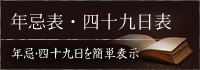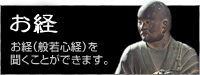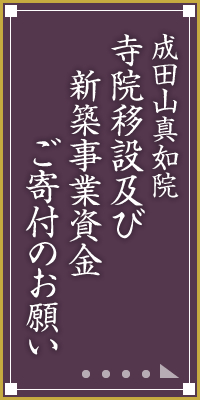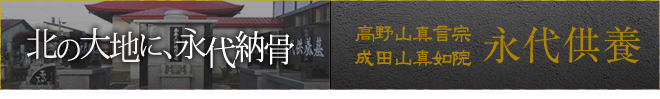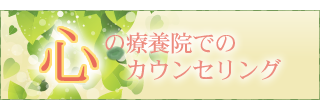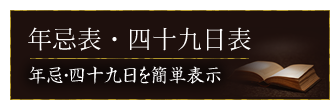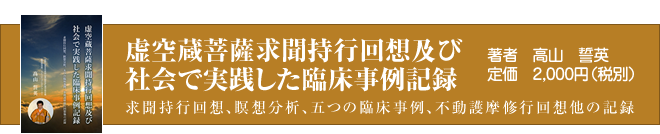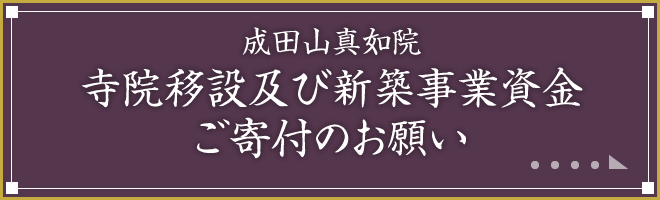明恵、夢を生きる(故河合隼雄著)
〈更新日: 奎和6年11月8日 〉 ※写真が掲載されている場合は、クリックすると拡大表示されます。
「明恵、夢を生きる(故河合隼雄著)」を読み終わって
故河合隼雄先生は、亡くなられて最早17年になる。
平安末期から鎌倉初期に生きた真言宗僧侶明恵上人の「夢記」を題材に著書が記述されている。
故河合隼雄先生は、京都大学数学科出身で有りながらユング心理学を研究され、日本に初めて心理学を紹介し発展させられた方である。そして、先生の専門分野に「夢分析」という心理学分野を初めて日本に紹介された方でもある。晩年は、文化庁長官として活躍されたが惜しくも病気にて逝去された。
故河合先生の記述本から明恵上人とその夢の一部を紹介してみたいと思う。
明恵上人は、承安三年(一一七三)に生まれている。たまたま同じ年に親鸞聖人も生まれている。
実に奇遇である。この頃は、平安朝貴族社会が崩壊し平清盛が政治の実権を握っていた時代も収束して、源頼朝の武家政治が鎌倉幕府中心に今や始まろうとする時代の頃である。
この時代の日本は、目まぐるしく変化して何が正しくて、何に頼るべきか分からない時代であった。
明恵は、平重国の長男として武家の家に生まれている。しかし、明恵八歳の時に父重国は、治承四年(一一八〇)鎌倉に挙兵した源頼朝の乱に巻き込まれ戦死している。また母は、重国の亡くなる少し前に亡くなっている。この為明恵は、幼くして両親を亡くし天蓋孤独な生き方を強いられたのである。
父の死後、明恵は、母方の叔父上覚を頼って京都高雄山神護寺(現存)に入山する。この時から僧侶としての生き方が始まる。しかし、当時一般社会では、戦乱に巻き込まれ、治承四年の大凶作により餓死者が溢れ、京都のあらゆる所に死者が散乱していたと言う。(鴨長明、方丈記より)
この為明恵は、父母の死や飢饉による餓死者を目の当たりにして心的に深く感じる所があったようだ。
そしてこの事実が、その後の明恵の心の内的発展に大きく影響したと故河合先生は分析している。
九歳の時に高雄に入山した際の夜に見た夢を初めて記録に残していると故河合先生が紹介する。
これは、高雄に明恵が入山して仏典の勉学を始めたのだが、内容の不明な所を同僚僧に尋ねるが答えられない。所が夢の中で「インド僧が表れ、不明な点を解き明かしてくれた」夢を見る。
また、「自分を育ててくれた乳母の身体が切り刻まれてバラバラに成る夢」も見ている。
何ともすざまじい内容であるが、故河合先生は、西欧各地に残っている身体をバラバラに刻むと言う夢は、ユングが錬金術と関連付けて分析している点を指摘している。
これは、未分化の原料が分離や分解を通じて製品が出来てゆく過程と同じで、人間の人格が未分化な自己を壊して自己の個性化実現の為に、身近な自己に近い物を切り捨てることと同じ事と指摘する。
「明恵がインド渡航への憧れ、釈迦への憧れがインド僧と言う暗示に転じた夢」を見ることは、明恵自身が幼少期の未熟な人格から次の人格へと上昇しようとしている暗示であると先生は指摘する。
このように夢は、自己の周辺に起きている所で、現実に隠れている背景を補完する部分を夢で見せてくれるのだと、故河合先生は、夢が持つ凄さを強調する。
「共時性」と言って、自分が見た夢が正夢の如く現実に表れる点も強調する。
明恵が修法中に「大湯屋の軒の雀の巣の中に蛇が入った。雀を助けてやりなさい」と近くに居た小僧に伝えた所、「どうしてこんなにも暗いのに明恵上人は、分かるのだろうか」と不思議に思いながらその場所へ駆けつけて見ると言われた通りだった。
このように不思議な事ばかり起こるので、人々は、明恵を「仏や菩薩が此の世に仮に出現した人だ」と伝えたと言う。すると明恵は、「こんなことは、大した事ではない。人間には自然に出来ることだ」と皆を諭したと言われている。
私も札幌分院を建立する際、夢をよく見た。良く覚えている夢に、「建物の首いっぱいに水が溢れているのに建物も自分も全く動じていない夢」や「ある建物を夢を中で見ていた時、建物が金ぴかに光っている夢」を見たことがある。今振り返って夢と実際現実とを比較して見ると、出発当初から多額の借入れ金で首が回らなくなる所まで来ていた筈なのに何故か乗り超えてしまっていること。
未来に立派なお寺の完成がある事を暗示していた夢であったように覚える。
このような夢の事を「共時性」とユングは言っている。
私自身も経験した事が明恵上人を紹介する中で再度理解出来た思いだ。